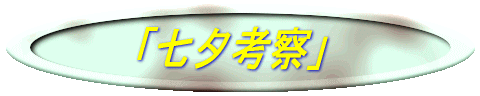
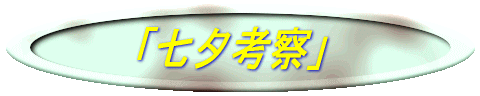
1. 七夕の紀元は
七夕は中国古来の伝説に基づく行事。仏教と関係が深い。中国では、織女星(こと座の1等星ペガ)は天帝の娘とされていた。天帝は織女の伴侶を求めて、牽牛星(わし座のアルタイル)に目をつけた。牽牛は働き者で農耕の主力である牛を牽く仕事が得意だった。→ 無事に結婚。
新婚アツアツの夫婦は仕事をしなくなった。→ 天帝(注1)は怒って、2人を天の川を隔てた両端に離してしまった。但し、1年に1度だけは会えるように計らった。→7月7日
(3世紀の晋の時代の文献に7月7日という日が登場する)(注2)
2. 七夕を何故“たなばた”と読むの?
七夕伝説と行事は、奈良時代に仏教とともに日本に伝わった。当時、日本には似たような伝説があった。→ 棚機津女(たなばたつめ)の伝説(古事記)
タナバタツメは織女。村の災厄を除いてもらうため、水辺で神の衣を織り、神の一夜妻となるため、機屋で神の降臨を待った。(神が降臨したのが7月7日という記載あり。)
⇒ 中国の七夕伝説と日本の棚機津女の伝説がミックスして、後に伝わった。
3. 天の川とは何なの?
昔は、天の川を眺めて、地上の川が天上に映ったものと考えた。
北海道(アイヌ)では石狩川、インドではガンジス川、エジプトではナイル川。
中国では、黄河が銀色に映じているので銀河と名付けた。
実際は、無数の星の集まり。太陽系(地球を含む)は銀河(Galaxy)の一部。
我々(地球)は銀河の内側から見ている。ペガとアルタイル間の距離は16光年。とても
牽牛と織女が会える距離ではない。
4. 五節句とは?
奈良時代に定めた節句。陰陽学では奇数は“陽”だが、同じ奇数が重なると陰になる。
1月1日 人日(じんじつ)の節句 正月
3月3日 上巳(じょうし)の節句 ひな祭り
5月5日 端午(たんご)の節句
7月7日 七夕(たなばた)の節句
9月9日 重陽(ちょうよう)の節句
要は、季節の変わり目。
(注1)
中国では、天界を管轄するものを天蓬元帥と呼ぶ。織女伝説の頃の天蓬元帥は“猪八戒”。
猪八戒は女癖が悪く、酔った勢いで嫦娥(じょうが)姫(月の神さま)をレイプする。
このため天界を追われて死刑となる。転生輪廻からすると人間に生まれ変わるはずだったが、誤って雌ブタの胎内に入り、黒ブタの妖怪となった。成長してからも好き放題をやったが、後に、玄奘三蔵に弟子入りし、
孫悟空、沙悟浄らとともに天竺まで経典を求める旅に出かける。⇒ 般若心経
(注2)
7月7日と定められたのは、仏教に大いに関係ありという説。
旧暦4月8日(釈迦の誕生日)から290日(十月十日)を引くと、大体、旧暦7月7日に
なる。つまり、釈迦は牽牛と織女のハネムーン・ベビーという説。